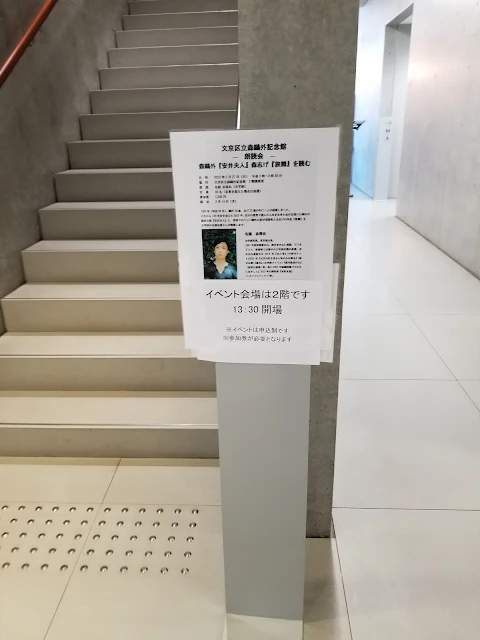日曜日は湯島天神の梅見と、久しぶりに千駄木の森鴎外記念館に行ってきた。
地味なイベントではあるが、文学座の名越志保さんの朗読会に参加した。
1本目の朗読作品は森鴎外「安井夫人」、この作品、知らないので事前に調べると青空文庫に載っていた。
安井仲平という江戸時代のお役人とその奥さんお佐代さんの苦労話で、「渋江忠斎」と同じく実話に基づいている。
朗読のもう1本は、森鴎外の奥さんの森志げの書いた「旅歸」(たびがえり)、こちらは森家そっくりの家の出来事をユーモラスに描いたものである。
まず「安井夫人」。
安井仲平というブサイクでマジメなお役人が、村一番の美女でしかも14才年下のお佐代さんに好かれて結婚してしまうという意外??な話である。
ただ安井仲平さんの場合、「努力」と「忍耐」の人格者で、幼少時から外見を馬鹿にされて、笑われても腐らずに勉学に励み、役人となり、地道に働き、30才の時にこの縁談を得たというのだ。
「滄洲翁は江戸までも修業に出た苦労人である。倅せがれ仲平が学問修行も一通り出来て、来年は三十になろうという年になったので、ぜひよめを取ってやりたいとは思うが、その選択のむずかしいことには十分気がついている。背こそ仲平ほど低くないが、自分も痘痕があり、片目であった翁は、異性に対する苦い経験を嘗なめている。識らぬ少女と見合いをして縁談を取りきめようなどということは自分にも不可能であったから、自分と同じ欠陥があって、しかも背の低い仲平がために、それが不可能であることは知れている。仲平のよめは早くから気心を識り合った娘の中から選び出すほかない。」
「一番華はなやかで人の目につくのは、十九になる八重という娘で、これは父が定府じょうふを勤めていて、江戸の女を妻に持って生ませたのである。江戸風の化粧をして、江戸詞ことばをつかって、母に踊りをしこまれている。これはもらおうとしたところで来そうにもなく、また好ましくもない。」
「あちこち迷った末に、翁の選択はとうとう手近い川添かわぞえの娘に落ちた。川添家は同じ清武村の大字おおあざ今泉、小字こあざ岡にある翁の夫人の里方で、そこに仲平の従妹いとこが二人ある。妹娘の佐代さよは十六で、三十男の仲平がよめとしては若過ぎる。それに器量きりょうよしという評判の子で、若者どもの間では「岡の小町」と呼んでいるそうである。どうも仲平とは不吊合いなように思われる。姉娘の豊とよなら、もう二十はたちで、遅く取るよめとしては、年齢の懸隔もはなはだしいというほどではない。豊の器量は十人並みである。」
「お豊さんは手拭いを放して、両手をだらりと垂たれて、ご新造と向き合って立った。顔からは笑みが消え失せた。「わたし仲平さんはえらい方だと思っていますが、ご亭主にするのはいやでございます」冷然として言い放った。お豊さんの拒絶があまり簡明に発表せられたので、長倉のご新造は話のあとを継ぐ余地を見いだすことが出来なかった。」
「川添のご新造は仲平贔屓びいきだったので、ひどくこの縁談の不調を惜しんで、お豊にしっかり言って聞かせてみたいから、安井家へは当人の軽率な返事を打ち明けずにおいてくれと頼んだ。そこでお豊さんの返事をもって復命することだけは、一時見合わせようと、長倉のご新造が受け合ったが、どうもお豊さんが意を翻ひるがえそうとは信ぜられないので、「どうぞ無理にお勧めにならぬように」と言い残して起って出た。」
「長倉のご新造が川添の門を出て、道の二三丁も来たかと思うとき、あとから川添に使われている下男の音吉が駆けて来た。急に話したいことがあるから、ご苦労ながら引き返してもらいたいという口上を持って来たのである。」
「「お帰りがけをわざわざお呼び戻しいたして済みません。実は存じ寄らぬことが出来まして」待ち構えていた川添のご新造が、戻って来た客の座に着かぬうちに言った。「はい」長倉のご新造は女主人の顔をまもっている。「あの仲平さんのご縁談のことでございますね。わたくしは願うてもないよい先だと存じますので、お豊を呼んで話をいたしてみましたが、やはりまいられぬと申します。そういたすとお佐代が姉にその話を聞きまして、わたくしのところへまいって、何か申しそうにいたして申さずにおりますのでございます。なんだえと、わたくしが尋ねますと、安井さんへわたくしが参ることは出来ますまいかと申します。」
「長倉のご新造はいよいよ意外の思いをした。父はこの話をするとき、「お佐代は若過ぎる」と言った。また「あまり別品でなあ」とも言った。しかしお佐代さんを嫌きらっているのでないことは、平生からわかっている。多分父は吊合いを考えて、年がいっていて、器量の十人並みなお豊さんをと望んだのであろう。それに若くて美しいお佐代さんが来れば、不足はあるまい。それにしても控え目で無口なお佐代さんがよくそんなことを母親に言ったものだ。」
「長倉のご新造が意外だと思ったように、滄洲そうしゅう翁も意外だと思った。しかし一番意外だと思ったのは壻殿むこどのの仲平であった。それは皆怪訝かいがするとともに喜んだ人たちであるが、近所の若い男たちは怪訝するとともに嫉そねんだ。そして口々に「岡の小町が猿のところへ往く」と噂した。そのうち噂は清武一郷に伝播でんぱして、誰一人怪訝せぬものはなかった。これは喜びや嫉そねみの交じらぬただの怪訝であった。」
さて、この物語の私なりの着眼点は、外見上の短所のように直せない短所があるなら、その短所を無理に直そうとはせず、別の長所を作る方がいい、ということである。
短所を直してもフツーになるだけで突出するわけではないので、あんまり意味がないということ。
でも、別の長所を作れば突出するので、何らかの意味で非常に豊かで魅力的な人物になれるのである。
また、直せない短所というのは、自分は気にしていても、他人はそれほど気にしていないものだ。
もっとも外見上の全ての短所に該当するとはいえず、物事には限度があるとは思うのだが、たいていの短所はそれほど気にする必要はないのではないか。
次は「旅歸」という森志げの作品。
旅から帰った鴎外と思しき文学博士の吉井先生、その奥さんの藤子とのやりとりが物語の中心である。
最初、とりさんという幼い子供が喋っていて、これってたぶん森茉莉のことかと思ったが、一家には子供が全部で3人いる。
後半になると、子供たちが寝付き、夫婦ふたりで葡萄酒を静かに飲みながら話す場面となる。
藤子が、「あなたって、悪いことをするから憎たらしいのではなくて、悪いことをしないのが憎たらしいのよ」とか言うのだが、吉井先生の方も、「鏡の前の女の顔というのは違うのだよね、自分の顔を鏡で見ている時の顔と、見ていない時のふとした顔とでは」とか言って、お互いに色気がない色気がないと言いあうのだが、結局、電気をつけたままにしましょう、ということになって物語は終わる。
以前ブログに書いたようにそもそも森志げは鴎外40才のとき、22才で結婚した。
鴎外によると彼女は「美術品の如き妻」で、引き算をしてみると18才も年下。
この話を聞き、私はそのようなご利益にぜひ、あずかりたいものだなあ、とは思ったが、、、ただ、学芸員の女性の補足の解説を聞き、考えさせられた。
実は、志げさんは鴎外と再婚する前は、大銀行家の御曹司で美男子のわたなべ君と結婚していたのだ。
が、わたなべ君は浮気性で、芸者との関係がばれて離婚となった。
鴎外との再婚は、彼女にとってある種の妥協で、わたなべ君に対する復讐(リベンジ)の意味もあったと思う。
結婚後鴎外は彼女に尽くした。
これも納得できることだ。
ここで私は先ほどの「安井夫人」の一節を思い出してしまう。
「わたし仲平さんはえらい方だと思っていますが、ご亭主にするのはいやでございます」
まあ、こちらの方が現実ではないか。