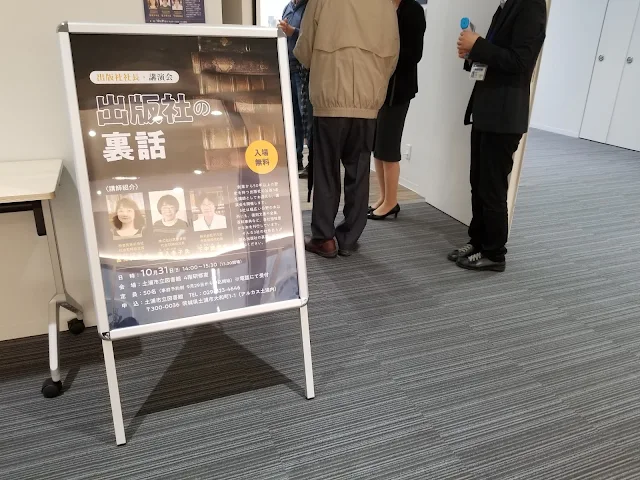7月、ワインの師匠T先生に旅先のおみやげを渡すため、私はキャプラン東京教室を訪ねた。
しかし、その時は到着時間が早すぎて先生は不在だった。
私は受付の男性に、先生の好きそうなピーナッツのおつまみの袋を渡し、教室を出たのだった。
その約4か月後、私はついにワイン講座で先生と再会した。
ええと、先生、約1年半ぶりですよね??
ステイホームが契機となり、すっかり足が遠のいた受講生も何人かいるようだが、見覚えのある受講生仲間が何人か座っていた。
おお、懐かしい!!
ピュリニーモンラッシェをズバリ言い当てたSさん(女性)も来ている。
さて、久しぶりに先生の講座を聞いたが、先生の講座はいつもよく練られている。
内容は楽しいし、人格的にもやはり、素晴らしい先生である。
今回の講座ではラングドック(Languedoc)のワインをテイスティングしたのだが、初めてのブドウ品種が2種類あった。
1つはモーザック(Blanquette de Limoux Elegance)、もう1つはピクプールブラン(PICPOUL DE PINET)。
前者は最古のスパークリング産地とも言われるところのNVで、後者はAOC(原産地呼称)の白ワインである。
いずれも口溶け時のファーストインプレッションはよかったし、フルーティーでおいしいが、少々退屈な味であった。
また、カリニャン、シラー、グルナッシュのブレンドを2種類試したが、一方はヴィンテージが古く、熟成しすぎだった。
もう一方はシラーの強烈なフルボディーで、香りも味も申し分のない高価格帯のワインと思い、シンプルなのでカベルネソーヴィニヨン75%の方(MAS DE DAUMA GASSAC)だと思って意見を上げたのだが、それはハズレ。
この2つの判別はみんな迷ったようだが、Sさんによれば、カベルネ75%の方はカベルネ独特の香りがしたといい、彼女にとっては簡単な判別だったようである。
アフターの飲み会は4人でコレド室町にある大衆居酒屋風のワインバーへ。
メニュー表に載っている当店名物の「こぼれシャンパン」って何だろう??
初入店の私だけが知らなかった。
最初の乾杯のため「こぼれシャンパン」を4人分頼んだが、これは、店員がシャンパンをグラスギリギリまで注いでくれる、という太っ腹な演出のものだった。
ああ、この演出を見ていると、ABCクッキングを思い出すなあ、、、
ABCクッキングでは、計量スプーンにしょうゆなどを入れるとき、私はいつも適当に計量をするので、料理の先生からよく注意されるのであった。
「表面張力でぷるぷるになるまでちゃんと入れてください!!」
「はい、すみません、、、」
これをシャンパンで実行するということか。
いや、でも、よく考えると不正確である。
店員はこぼれる寸前で注ぐのをやめたので、正確には、こぼれシャンパンではないぞ。
まあ、こんな感じで私がくだらないことを言っても、先生の方が一枚上手である。
シャンパンを注ぎ終えた店員に向かって、先生がおもしろいことを言った。
「店員さん、ちょっと聞いていいかしら??」
「はい、何でしょう。」
「失礼ですが、、、以前頼んだ時と比べてグラスがずいぶん小さくなってません??」
!!!(一同)
「ええと、すみません、以前は「こぼれスパークリング」でしたが、今日は「こぼれシャンパン」なのです、、、」(と店員)
「なるほど。ごめんなさいね。わたくし、こういうことだけはよく覚えてまして。」
「いや、先生はさすがです。酒飲みにとってそれは重要な問題ですからね。」
「そうそう、先生は代表で聞いてくれたのよ。」
シャンパンで乾杯した後、そこから2時間以上、楽しい話をして盛り上がった。
店を出たのは10時近くだったが、店を出る時、近くのカウンター席でずっと1人で飲んでいた派手な身なりの女性が私たちに声をかけてきた。
「今日はどうも、ありがとうございます。」
「何でしょう??」
「最近はいつも1人で飲んでいるのだけど、今日はみなさんのお話を聞かせてもらい、とても楽しく飲めました。」
「それはよかった。」
コロナ禍で、すっかり1人飲みが定着したものだが、女性は話好きなので、1人飲みではつまらないし、さみしさを感じるだろう。
彼女が楽しく話して飲めるようになれる日が早く来るといいのだけど。






.jpg)

.jpg)